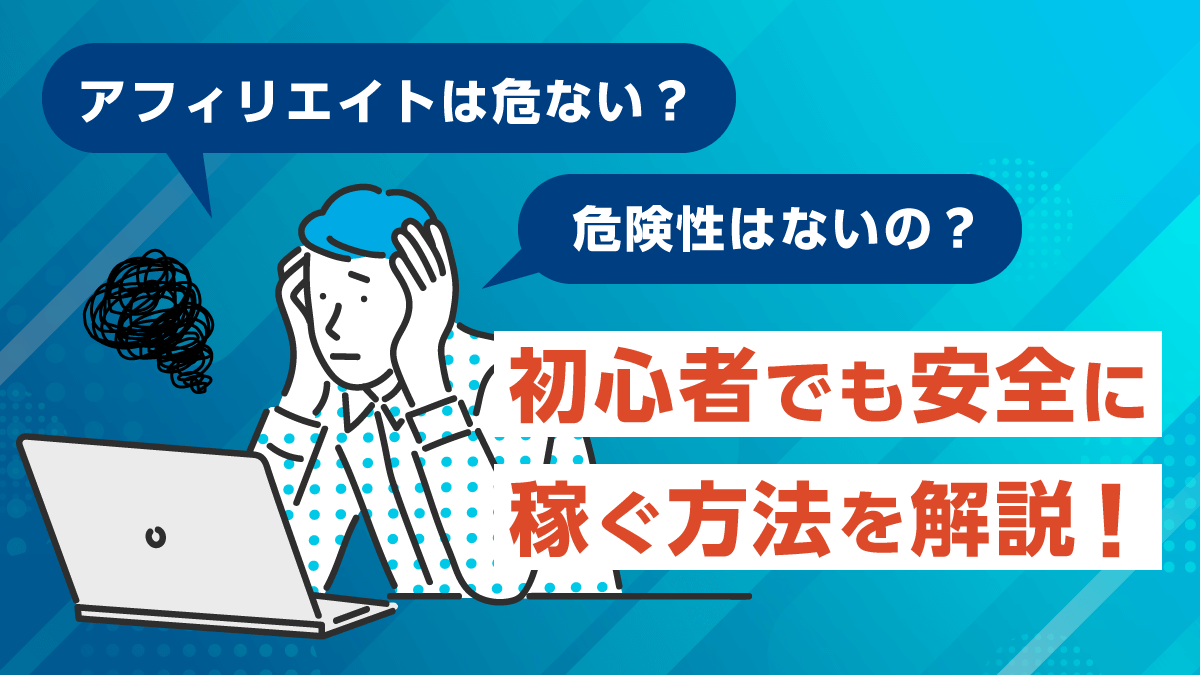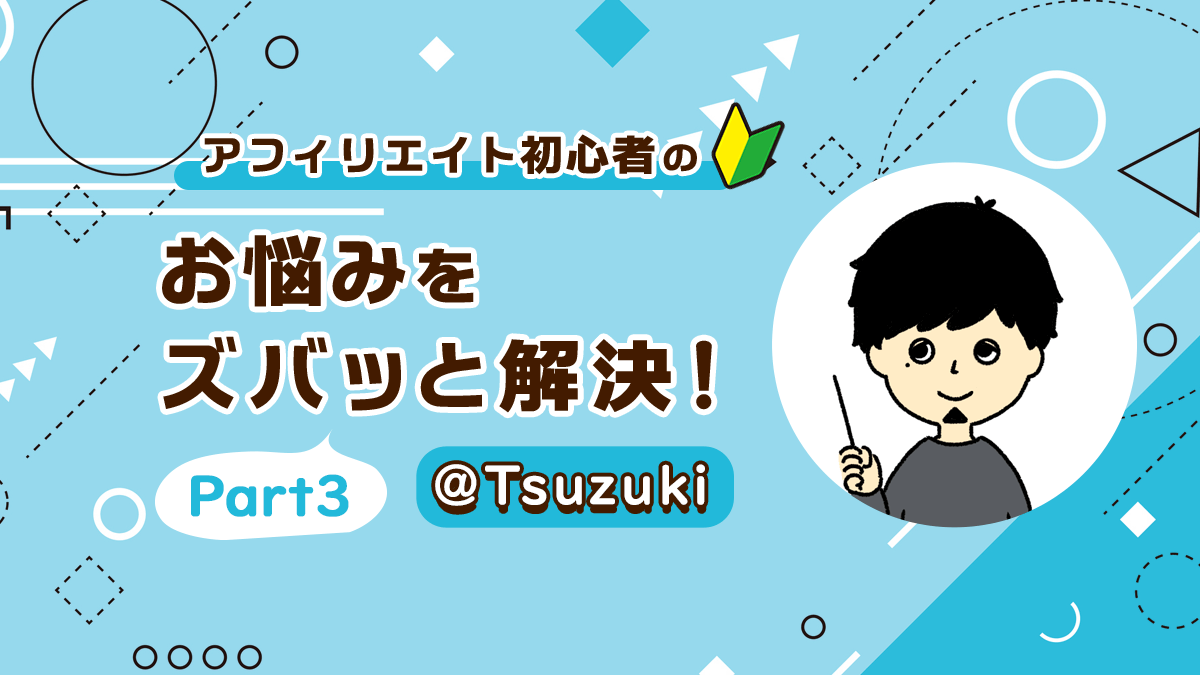皆さんこんにちは。税理士の田中保則です。
「アフィリエイターと確定申告」をテーマとしてご紹介する全3回シリーズのコラム第2回です。
第1回は「確定申告とは?&確定申告が必要な人」について解説を行い、アフィリエイト収入が「事業所得」もしくは「雑所得」であるということまで説明しました。
そこで今回は、その所得からどのように税金を計算し申告するのかという、「申告の種類と所得税計算の基本構造」を解説していきます。
それではコラムを進めていきましょう。
確定申告の種類
青色申告と白色申告
第1回では確定申告が必要なかたについてご紹介しましたが、確定申告にはいくつかの種類があります。まず分類することができるのは「白色申告」「青色申告」です。よく略して「しろ」とか「あお」などと呼ばれるものです。
「なぜ青色?」と思うかたもいらっしゃるでしょう。実は少し前までは白色申告と区別するため、青色申告では確定申告書の表紙に青色の用紙を使って申告していました。その名残で今でもその名前が利用されているのです。
次に「青色申告と白色申告の違いは?」という疑問に答えていきましょう。
白色申告とは、簡単な方法で記録して所得金額を算定し、申告および納税する方式のことをいいます。
一方、青色申告とは、正しい申告をするため一定の会計帳簿に正確な記帳をし、それに基づき損益計算書や貸借対照表を作成して、申告書の作成および納税をおこなっている税務申告の方式のことをいいます。
前提として、第1回でお伝えした通り、青色申告は「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出している「事業所得」のかたが対象となります。それ以外のかたは必然的に白色申告となります。今一度ご自身がどちらに当てはまるか確認をしておきましょう。
青色申告の優遇措置とは
手続き面だけを見れば白色のほうが断然簡単でよいと思うのですが、世間では確定申告といえば「青色」というイメージが強いと思います。それはなぜかというと青色申告をすることで、税額の算定上、様々な優遇措置が設けられているからです。主なものを簡単に説明します。
1.青色申告特別控除
事業所得などが生じる事業を営んでいる青色申告者が正しい会計帳簿を作成し、それに基づき作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し期限内に申告した場合には、原則としてこれらの所得から最高55万円を控除することができます。
- ※55万円の青色申告特別控除を受けることができる人で法令に基づいた電子帳簿保存又はe-Taxによる電子申告を行っている場合は、65万円の控除をすることができます。
また現金出納帳や経費帳などのような簡単な会計帳簿だけの場合は10万円を控除することができます。
2.青色専従者給与
青色申告者と生計を一にしている(※1)配偶者やその他の親族で一定の要件に該当する場合は、それらの人に支払った適正な金額の給与は必要経費に算入することができます。
- ※1.生計を一にする:日常の生活の資を共にすることをいいます。
会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、1 生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、2 日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。 - ※2.青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
3.貸倒引当金
事業所得を生じる事業を営む青色申告者で、その事業で生じた売掛金などの貸倒れによる損失見込額として、年末における帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れ必要経費として認められます。
4.純損失の繰越しと繰戻し
事業所得などに赤字がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越すことができます。また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
以上のように青色申告には各種の優遇措置が設けられていますが、先にお伝えしたとおり青色申告を行うためには、「開業届出書」等書類以外に、税務署に「所得税の青色申告承認申請書」などの書面を事前に提出しておく必要があります。
提出期限は、青色申告しようとする年の3月15日までです。ただし、1月16日以後に事業等を開始したときは、その事業等開始後2ヶ月以内に税務署長に申請することになっています。
したがって、「所得税の青色申告承認申請書」の提出がなかった場合は控除がない白色申告となりますのでご注意ください。
申告書の様式「A」「B」の違い/アフィリエイターはどちらを使えば良い?
確定申告をおこなう場合、申告書にはその様式が2種類あります。
それぞれ申告書は「確定申告書A」と「確定申告書B」というネーミングがされており、その違いは以下のとおりとなります。
- 確定申告書A
申告する所得が給与所得等、その他雑所得・配当所得・一時所得のみで、予定納税額のないかたが使用できる - 確定申告書B
所得の種類にかかわらず使用できる
アフィリエイターが確定申告を行う場合は所得の種類にかかわらず使用できる「確定申告書B」の様式を利用して確定申告をすることになります。
所得税の基本的構造
ここからは具体的な税金の計算の流れを紹介していきますが、基本的には構造は以下のとおりとなります。
所得から所得控除を差引いて課税される所得金額を算定し、それに税率を掛けて所得税額を算出する。さらに求めた所得税額から税額控除があればこれを控除し、納めるべき税額を求めることとなります。

所得計算
では所得とは具体的に何を意味するのでしょうか?
所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額のことを指します。
つまり、図で表すと所得計算の基本構造は以下のとおりとなります。

これを青色申告のアフィリエイターの所得計算にあてはめてみましょう。

アフィリエイトで得た収入から、経費(例として挙げた家賃・ネット回線・水道光熱費等)を差し引いて残った金額です。
アフィリエイターの所得計算の詳細については第3回でご紹介しますね。
所得控除
次に所得控除について説明します。これは所得税額を計算するときに各納税者の個人的事情を加味しようという制度です。この制度はそれぞれの存在を認識していないために控除することを忘れてしまうといったことがよくありますので、確定申告をおこなうアフィリエイターの皆さんは所得控除の概要だけでも知っておくと大変有用です。
- 基礎控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 勤労学生控除
- 障害者控除
- ひとり親控除
- 寡婦・寡夫控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 地震(損害)保険料控除
- 医療費控除
- セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
- 寄付金控除
- 小規模企業共済掛金控除
- 雑損控除
会社員の場合は通常、会社で行われる年末調整で1〜11までは基本的に処理をされています。実際にお手元に源泉徴収票があれば、その記載を確認することができると思います。
1.基礎控除
基礎控除とは総所得金額などから差し引くことができる控除の一つですが、その控除額は下記の図の通り納税者本人の合計所得金額に応じて異なります。
| 納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
[令和3年4月1日現在法令等]
2〜8.扶養控除等
配偶者、子供などの扶養親族の状況や各々の家庭の状況を応じて、所得控除ができます。
9.社会保険料控除
その年に支払った金額社会保険料の全額を所得から控除することができます。
10〜11.保険料控除
その年に支払った生命保険料、個人年金保険料、介護保険料、地震保険料の額に応じて、所得控除ができます。
12〜13.医療費控除関係
納税者が、自分や自分と生計を一にしている配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合、次の式で算定した金額を控除することができます(最高200万円)。

また、医療費控除の特例として、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合で、自己がその年中に健康の保持増進および疾病予防の取組として一定の健康診査や予防接種などをおこなっているときは、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額のうち、1万2千円を超える部分の金額を控除額とするセルフメディケーション税制の適用を受けることができます。
なおセルフメディケーション税制は医療費控除との併用はできないため、この控除は通常の医療費控除との選択となります。
14.寄付金控除(ふるさと納税)
国や地方公共団体や日本赤十字等などに支出した寄付金で教育や科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献等に当たられたものについては所得控除することができます。いわゆる『ふるさと納税』もこの控除の一部であり、下記の算式により控除額を求めます。

15.小規模企業共済掛金控除
小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合には、その支払った全額について所得控除が受けられます。
16.雑損控除
災害又は盗難若しくは横領によって資産に損害を受けた場合で、一定の要件にあてはまる場合には、次の[1]と[2]のうちいずれか多いほうの金額を所得控除とすることができます。
- [1] (損害金額+災害等関連支出の金額−保険金等の額)−(総所得金額等)×10%
- [2] (災害関連支出の金額−保険金等の額)−5万円
税額算定
所得税額の算出は課税所得金額の大きさにより、5〜45%までの超過累進税率(※)となっていますが、実際に課税総所得金額の税額を計算するときは、下記の速算表によって税額を求めることができます。
- ※超過累進税率…所得税の税率は、所得が多くなるに従って段階的に高くなり、納税者がその支払能力に応じて公平に税を負担するしくみとなっています。。
[所得税の速算表]
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
[令和3年4月1日現在法令等]
税額控除
税額控除とは、二重課税の排除や特定の政策を推進することを目的として設けられている制度です。主なものを以下にご紹介します。
1.配当控除
剰余金の配当などの配当所得があるときには、一定の方法で計算した金額の税額控除を受けることができます。
2.特定増改築等・住宅借入金等特別控除
住宅ローン等を利用して住宅を購入等した場合で、一定の要件にあてはまるとき、借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額を、数年にわたり所得税額から控除するという特例のことです。
以上のとおり、今回は「確定申告の種類と所得税計算の基本的構造」というテーマでご説明しました。
確定申告に馴染みのないかたにとっては少し難しい内容だったかもしれませんが、税金がどのように計算されているのかを知ることはアフィリエイターにとっても非常に大切です。ぜひ理解を深めてくださいね。
次回は最終回として『アフィリエイターの所得計算』というテーマでお伝えします。今回の「所得計算」という項目について、アフィリエイトの観点からさらに詳細なご説明をしますので、次回もお楽しみに!
- ※ご不明な点は税務署や税理士にご相談ください。
ご注意ください
- 本記事の内容は、2022/02/03更新時点の情報です。更新日より期間が経過している場合など、状況により現在の情報とは異なる可能性があります。
- 一部、体験談などの執筆者の個人的な意見、株式会社インタースペース(アクセストレード)以外が提供するサービスの紹介が含まれる場合もあります。情報の内容には十分に注意しておりますが、万が一、損害やトラブルが生じた場合も責任を負いかねますので、内容をご確認の上ご自身の判断のもとでご利用ください。
- 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載等を禁じます。
 カテゴリーから探す
カテゴリーから探す
 タグから探す
タグから探す
- アフィリエイトを始めよう!
- 無料新規パートナー登録
- 広告主・代理店のかた
- 広告出稿はこちら